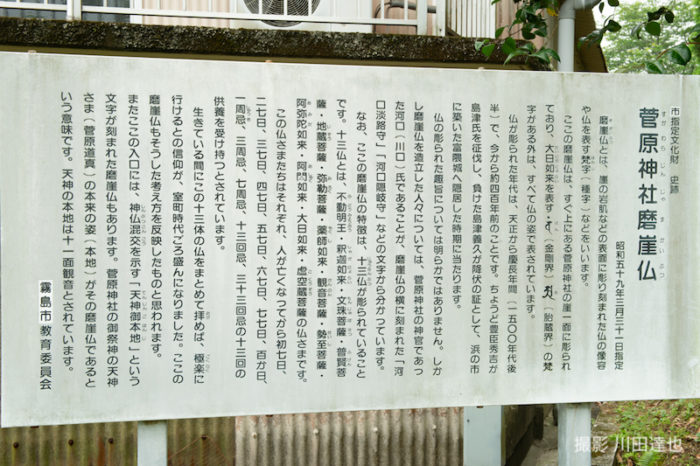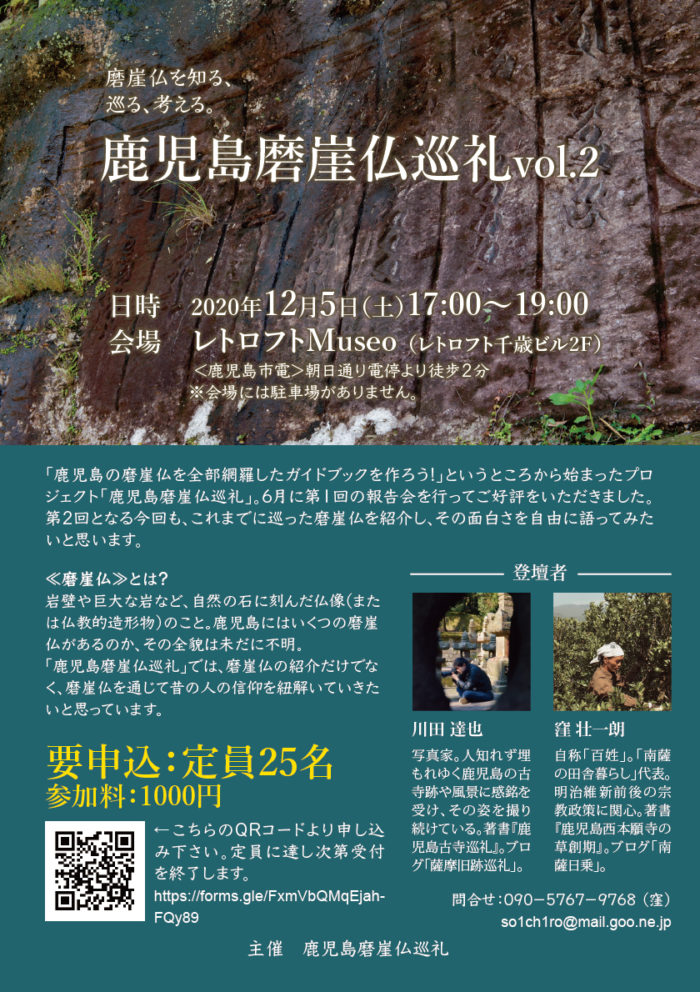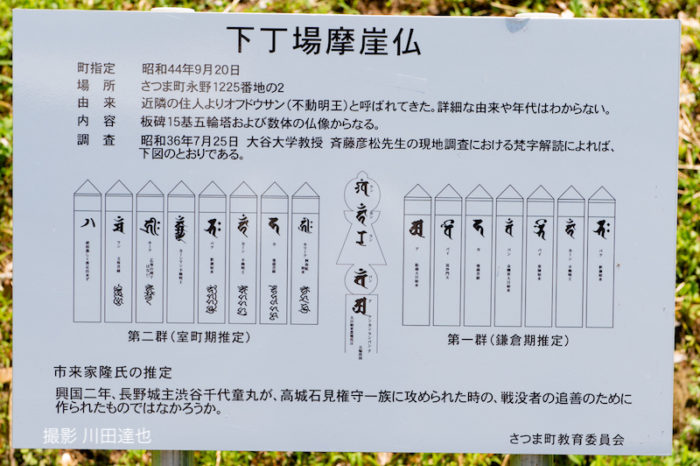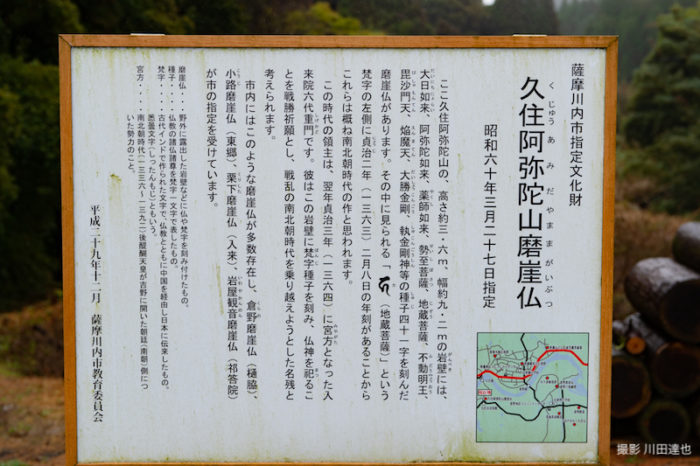竜ヶ城一千梵字仏蹟は、姶良市蒲生町下久徳にあります。

竜ヶ城磨崖一千梵字仏蹟の基調となるのは、大量の梵字です。岩壁が過剰なまでの夥しい梵字で埋め尽くされ、一ヶ所にまとめられた梵字の数では日本一だそうです。
竜ヶ城磨崖一千梵字仏蹟を前にして誰しも思うのは、どうしてこのように大量の梵字を刻む必要があったのだろうか、ということでしょう。しかも陀羅尼のような文章を刻むならまだしも、同じ梵字の繰り返しがほとんどですから、大量の梵字を刻むより、少数の大きくて立派な文字を刻んだ方がよかったのではないかと感じてしまいます。
しかしこの背景には、おそらく仏教の「数は力」思想があるのです。
日本において仏教の「数は力」思想の先蹤となったのは、奈良時代の「百万塔陀羅尼」です。宝亀元年(770)、陀羅尼を印刷した紙を納めた100万基もの木製小塔が作られました。100万基とはとんでもない数ですが、実際に100万基作られたと考えられています。「百万塔陀羅尼」の場合、大量なだけでなくかなり手も込んでいます。陀羅尼の印刷は日本最古の印刷物ですし(世界的にもかなり古い)、木製小塔も轆轤(ろくろ)が使われた精巧なものです。当時の最先端技術を使ったものといえるでしょう。
平安時代になると、10世紀の中国における越王銭弘俶(せんこうしゅく)の八万四千造塔の信仰が伝わります。「銭弘俶八万四千塔」はアショーカ王が八万四千の仏塔を作った故事を踏まえて作られた銅製の小塔で、実際に8万4000基作られたかどうかは定かでありませんが、かなり大量に作られたのは間違いありません。その実物もいくつか日本に伝来しました。なお「銭弘俶八万四千塔」のデザインは宝篋印塔のモデルになったとされます。

そして、おそらくは「銭弘俶八万四千塔」の伝来がきっかけになって、平安時代末期には小塔の多数造立が皇室や公家、僧侶、上級の武士たちの間に広まり盛行します。末法思想の高まりによって、「救いのない世界の到来」を感じた人びとが藁をもすがる思いで大量の小塔造立を行ったのです。その主なものは次のようになります。
| 保安3年(1122) | 白河法皇 | 法勝寺で五寸塔三十万基供養 |
| 天治元年(1124) | 白河法皇 | 五寸塔十万基造立 |
| 保延6年(1140) | 僧 西念 | 六万九千三百八十四本の卒塔婆造立供養 |
| 嘉応元年(1169) | 鳥羽法皇 | 八万四千基の泥塔を仁和寺紫金台寺で供養 |
| 承安4年(1174) | 藤原基房 | 泥塔一万基を造立し、妻の平産を祈願 |
| 養和元年(1181) | 後白河法皇 | 八万四千塔を蓮華王院で供養 |
| 建久元年(1197) | 鎌倉幕府 | 戦死者の冥福を祈り五寸塔八万四千基の造立供養 |
| 建仁3年(1203) | 源 頼家 | 病気平癒のため泥塔八万四千基の造立供養 |
| 建保元年(1213) | 源 実朝 | 八万四千基塔供養 |
| 建保4年(1216) | 後鳥羽上皇 | 七条院の菩提を弔うため八万四千基塔を仁和寺で供養 |
これらの造立数は、額面通り受け取ってよいものでしょうか。「八万四千」は大量であることを表す数字で、常にちょうど84,000のことを表すのではない、とされていますが、上記の表で具体的な数字が挙げられていることを見ても、少なくともこの時代では律儀に決めた数を作ろうという意志はあったようです。
数万基も作ったという小塔はどのようなものだったのでしょうか。もちろん、手が込んだ小塔を作るのは不可能でした。作られたのは、「泥塔(どろとう/でいとう)」と呼ばれる、泥を塔型で型抜きして焼成してつくる、ほんの数センチの塔でした。
泥塔自体は、奈良時代からあり、底部に小紙を納入するための小さな穴があるのが本来の形で、古くは小さなお経を収めていたのではないかと思われます。しかし平安時代の頃の泥塔は小孔がなくなっています。代わりに、小塔の塔身にお経の文字一字や梵字が刻まれていることが多いようです。このように簡易的に作成した小塔が無数に作られたのが、平安末期から鎌倉初期でした。

なお上記の表で、蓮華王院で八万四千塔を供養している後白河上皇は、三十三間堂(蓮華王院本堂)に1001体もの千手観音菩薩を安置しますが、これも「数は力」思想によるものと見て間違いありません。
鎌倉時代になると、「籾塔(もみとう)」と呼ばれる小塔が出現します。これは宝篋印塔の形をした数センチの木製の塔で、中には籾が入っています(宝篋印陀羅尼が納められる場合もある)。籾を仏舎利に見立てているのです。ご飯を「舎利」というのはここからきているのかもしれません。元来、宝篋印塔は、「銭弘俶八万四千塔」をモデルにしたものですから、小塔造立のためのデザインであったと考えられます。室生寺から発見された3万7387基の籾塔が有名です。これは室町時代(14世紀)に作られたものだそうです。
江戸時代に入ると、「数は力」思想が仏像に及び、大量の仏像の造立がたびたび見られます。最も典型的なのは「五百羅漢像」です。羅漢とは、お釈迦様の弟子の聖者です。大変個性的な方々で、それぞれ特徴を違えた500人の羅漢像が各地で造られました。埼玉の喜多院、東京の五百羅漢寺、京都の石峰寺、島根の羅漢寺などが有名です。京都の石峰寺の五百羅漢は伊藤若冲がデザインして石工に製作させたもので、元来は千体以上あったといいます。
江戸時代には「一字一石経」も各所で作られ埋められました。「一字一石経」とは、一つの小さな石にお経の文字を一文字だけ書いたものです。法華経の場合が多いのですが、法華経は約7万字ありますので、7万個もの石を拾ってそこに字を書いていくのは、ただ法華経を筆写するのに比べ非常な労力を要します。それなのに、石は結局バラバラになってしまうので文章の意味は失われてしまいます。これなどは、経典の内容よりも「数は力」思想によるものと考えないと理解できないでしょう。
また、「数は力」といえば、生涯で10万体以上の仏像を彫ったと言われる円空も思い起こされます。
このように、仏教の「数は力」思想は、日本の歴史を通じて見ることができます。神道の場合は、このように計画的に大量に何かを作るということは稀です。伏見稲荷大社の千本鳥居にしても、結果的にたくさんの鳥居が奉納されて成立したもので、仏教の場合のように「八万四千」など具体的な数を決めて最初から計画的に大量に作ろうとしたのとは違います。
しかし、歴史を通じて、常に仏教の「数は力」思想が貫いていたかというとそうでもなく、「量より質」が重視された時もありました。細かい検証はしていませんが、やはり小塔造立が流行した平安末期〜鎌倉時代と、江戸時代が、「数は力」思想が盛り上がった時と見るのがよさそうです。
ともかく、竜ヶ城磨崖一千梵字仏蹟の岩壁を埋める梵字群も、仏教の「数は力」思想によるものということは明白でしょう。もしかしたら、この磨崖仏が作られたのも、小塔造立供養が流行した平安末期〜鎌倉時代なのかもしれません。
【参考文献】
播磨定男『中世の板碑文化』
奈良国立博物館「銭弘俶八万四千塔」
https://www.narahaku.go.jp/collection/p-961-0.html